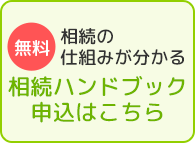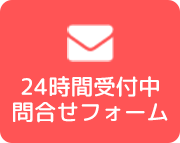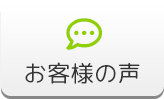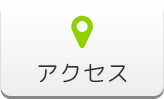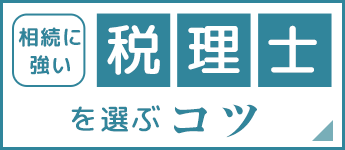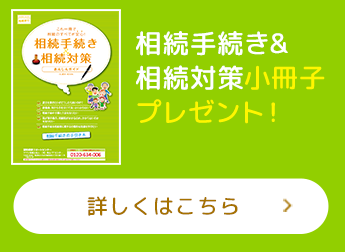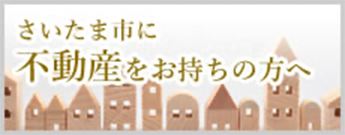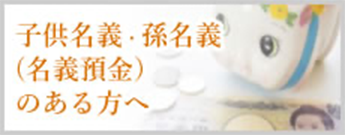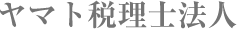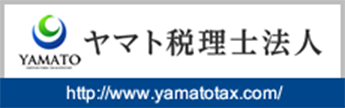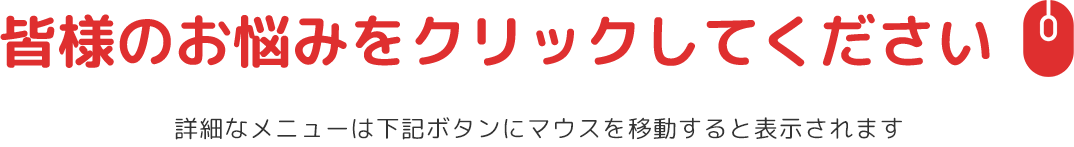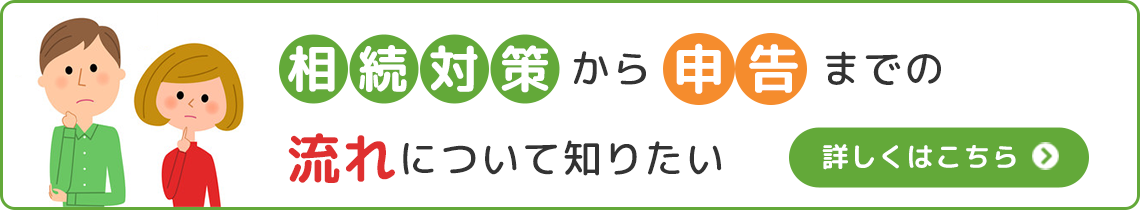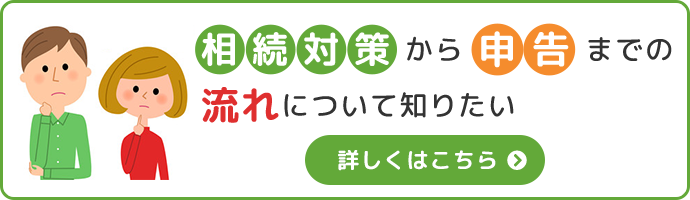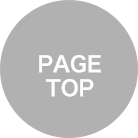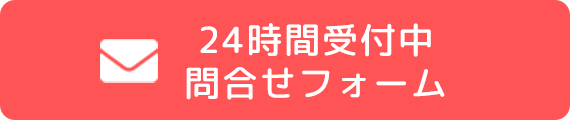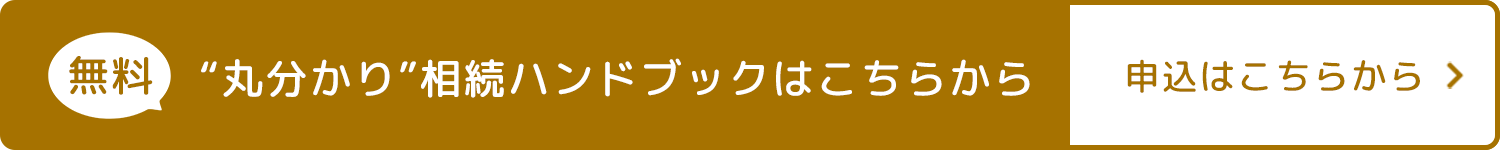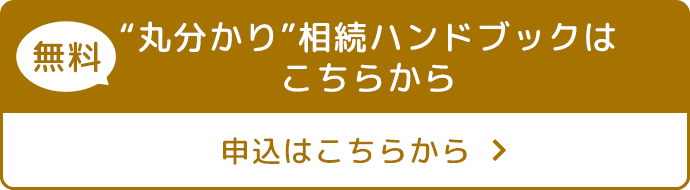家族名義預金について
相続税の申告にあたり、最も頭を悩ませるのが家族名義預金の申告だと思います。
銀行や証券会社にある金融財産は、一義的には名義人が真の所有者となります。
では、被相続人の遺品の中に、「誰も知らなかった孫名義の通帳」が出てきた場合はどうでしょうか。
答えは「実質的には被相続人のものなので、家族名義預金として相続財産に計上して申告する。」が正解です。
すなわち、被相続人が、自分の財産を孫名義の預金に分けていただけなので、実質的に被相続人のものだと判断されるのです。もしもこれが相続財産ではないと認められたならば、被相続人は全ての財産を生前に近しい若い世代の親族の名前の口座に移してしまえばよいことになります。

具体的にどんな預金が被相続人に帰属する家族名義預金となるのでしょうか。過去の裁判例によれば、次の二つの条件を満たしているものとされています。
一つ目の条件は、「家族名義預金の原資(預金の元となったお金)が被相続人の出捐(出したお金)である」ことです。例えば、3千万円の妻名義預金があったとします。もし妻がこれまで外に働きに出たこともなく、贈与されたこともないとしたら、それは被相続人のお金が基となっている可能性は高いと言えます。逆に、妻が実家の相続で多額の預金を手にしていたら、妻名義の預金は被相続人とは無関係である可能性が高いということになります。被相続人と関係ない原資のものは、他の条件がどうであれ相続財産とはなりません。
二つ目の条件は「家族名義預金の管理・運用を被相続人が行っている。」ということです。たとえば、先の孫名義預金のように、誰もその存在を知らなかったようなものは、明らかに被相続人が管理していたと判断できます。また、生前に被相続人から「お前の名前で貯金してあるよ」と言われていても、管理していたのが被相続人なら被相続人のものとなります。
では、妻がそれ専用に生活費を入金してもらっている口座はどうでしょうか。管理は妻が行っているので妻のものとしてよいのでしょうか。通説的には「ノー」、被相続人のものとなります。理由は、妻は被相続人の代理であり、被相続人の許可なく好き勝手に処分することはできないから、口座の帰属までは移動しないと考えられているからです。同じように、被相続人からもらった生活費で妻が貯めたへそくりも相続財産になります。
しかし、妻の年金受取口座などは原資に妻固有のものが含まれており、たとえここに生活費が混入していたとしても、口座全部が被相続人のものとは言えません。そのような場合には、口座に残っている金額の大小や、入出金の状況をみて判断する必要があります。
また、生前に贈与されたものであることが明らかなものは相続財産とはなりません。しかし、実際に通帳やカードがもらった人に渡っていなければ贈与は成立しないことにも注意が必要です。贈与契約書があるとか、贈与税の申告をしているとか客観的事実があると強いですが、それでも絶対大丈夫だとは言えません。中には、被相続人が勝手に契約書を作って勝手に孫の名前で申告しているケースなどもあり、そのような場合には贈与そのものが否認されることもあるのです。
最後に、相続が始まったら、まず、家族の名前の預金がどのくらいあるのか必ず確認してください。そのうえで、その人の収入や過去の経歴等からみて金額が相当か判断し、判断に困ったら専門家に相談してみるのが一番だと思います。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
|
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
|
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
|
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
|
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
|
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
|
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
|
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
|
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ


1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ


(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ


相続の無料相談会について
専門家による無料相談


無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
メールのお問合せはこちら