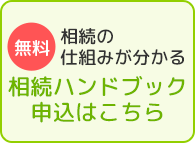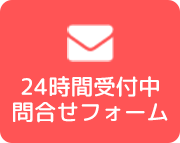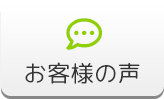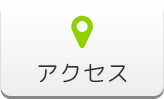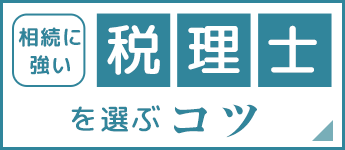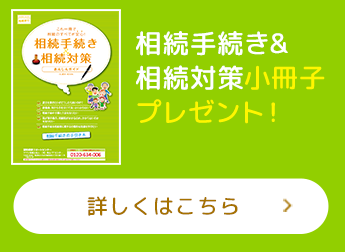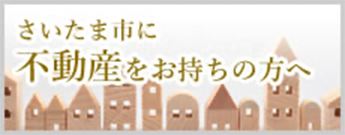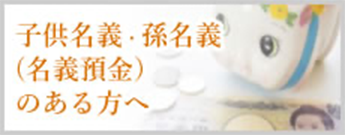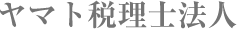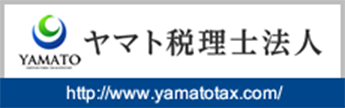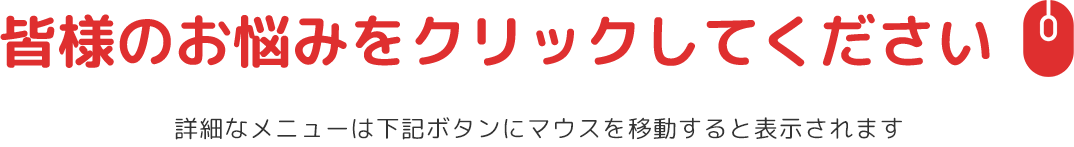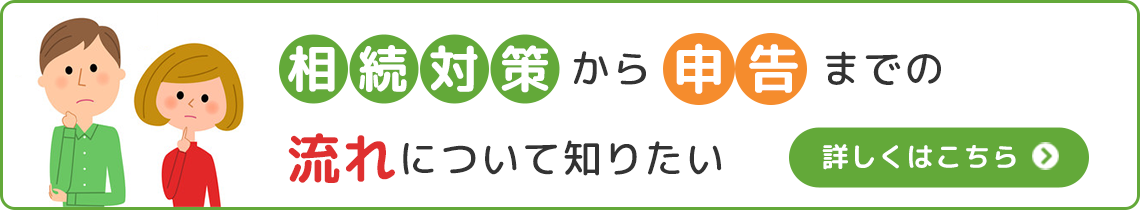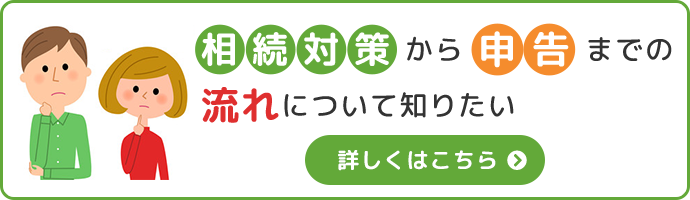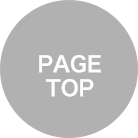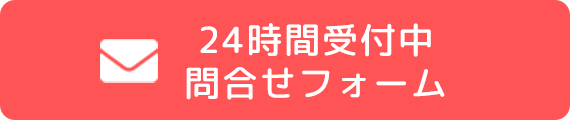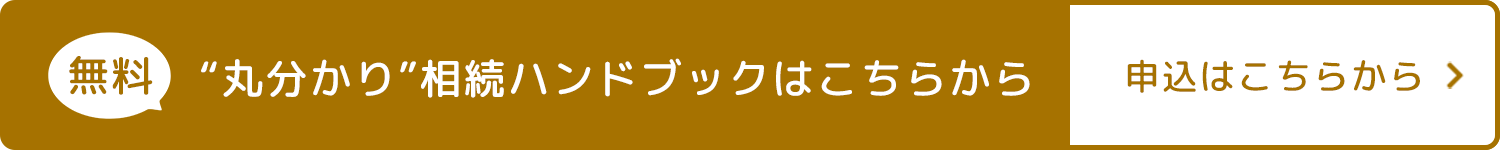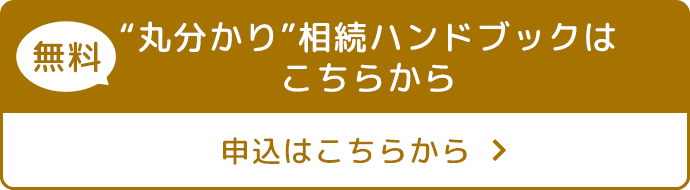【コラム】名義預金とは?対象となるもの・ならないものの判断基準と申告方法【相続税対策】


こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
相続税対策を検討する際、「名義預金」という言葉を耳にしたことはありませんか?一見、家族名義の口座であっても、税務署に“本当の持ち主”が誰かを厳しくチェックされるのがこの「名義預金」です。名義預金が相続税の対象になるかどうかは、預金の実質的な所有者によって判断されます。申告を誤ると、税務調査で追徴課税を受けるリスクがあるため、注意が必要です。この記事を読むことで、名義預金に関する誤解をなくし、安心して相続税対策に取り組むための知識が得られますので、ご家族の財産管理や相続に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
名義預金とは?相続税との関係
名義預金とは、通帳や銀行口座の名義人と、実際にその預金を管理・運用していた人物が異なる預金のことです。
形式的には子や孫の名義であっても、実質的な管理・資金の出どころが親や祖父母である場合、その預金は親や祖父母の財産と見なされ、相続税の課税対象になります。
なぜ名義預金が問題視されるのか?
名義預金は、相続税逃れを目的として「見せかけの贈与」が行われることが多く、税務署は厳しい目を光らせています。
特に、現金を子供名義の口座に移すだけで贈与が成立したと勘違いしているケースが多く、贈与契約書や資金移動の証拠がないと、贈与と認められません。
【判断基準】名義預金と見なされる預金の特徴
実質的な管理者が被相続人である
名義人が誰であっても、その預金の入出金の管理をしていたのが被相続人である場合は、名義預金と見なされます。
たとえば、子や孫名義の口座であっても、通帳や印鑑、キャッシュカードを被相続人が保管し、使っていた場合などです。
入金元がすべて被相続人の口座
預金の原資がすべて被相続人の収入や口座からの振替である場合も要注意です。
特に定期的に仕送りや振込があった場合、それが生活費ではなく明らかな貯蓄目的であれば、名義預金の可能性が高まります。
贈与の事実が確認できない
贈与契約書の作成や、毎年110万円以下に抑えた暦年贈与の記録がなければ、名義変更や振込だけでは贈与とは見なされません。
被相続人の死亡後に口座名義人が「贈与を受けていたつもり」と主張しても、税務署には通用しません。
【対象外】名義預金に当たらないと判断されるケース
-
贈与契約書の作成と贈与税申告が行われている
- 贈与が毎年110万円を超えていた場合、贈与税申告を行っていれば「贈与があった」という事実が立証されやすくなります。
また、贈与契約書を作成していれば、贈与の意図が明確であると判断されやすいです。
名義人が自分の意思で管理・運用していた
たとえば、子や孫が自身の判断で預金を引き出し、使っていた場合は、名義預金ではない可能性が高くなります。
通帳やキャッシュカードが本人の手元にあり、被相続人が関与していなければ、名義と実質が一致していると見なされます。
名義人が成人であり、預金が生活資金として使われていた
社会人になってからの給料の振込口座や、生活費、学費など日常的な出費が確認できる場合は、被相続人からの贈与ではなく本人の資産と認められることが多いです。
名義預金の調査方法と税務署の視点
税務署は相続税申告後に、名義預金の有無を調査します。
特に、被相続人と生前に同居していた家族の名義口座については、以下の点を重点的にチェックします。
・口座の開設時期と資金の出所
・被相続人の収入・資産との関係性
・入出金の頻度と用途
・通帳・印鑑の保管者
・名義人の収入状況と生活実態
このような調査により、形式ではなく「実態」で判断されるため、仮に名義を変えていても、証拠がなければ否認される可能性があります。
名義預金が発覚した場合の申告方法と注意点
相続税申告で「名義預金」として申告する
名義預金と判断された場合は、相続税の申告書に「その他の財産」として記載する必要があります。
記載漏れがあると、加算税や延滞税が課される可能性があるため、判断に迷った場合は税理士に相談することが望ましいです。
修正申告・更正の請求について
相続税申告後に名義預金が発覚した場合、5年以内であれば修正申告が可能です。
税務署からの指摘前に自主的に申告を行えば、加算税の軽減や回避につながることもあります。
名義預金を回避するためにできる対策
毎年の贈与は贈与契約書と贈与税申告をセットにする
単に名義を変えるだけではなく、贈与契約書を作成し、贈与税の申告を行うことで、税務署に「贈与の事実」を明確に証明できます。
通帳・印鑑は贈与を受けた本人に渡す
管理・使用権限が誰にあるのかが名義預金の判断基準になります。本人に実質的な管理を委ねていれば、名義預金と見なされにくくなります。
生前対策として専門家に相談する
名義預金の判断は非常に難しく、ケースバイケースです。
中小企業の経営者であれば、会社名義と個人名義の預金の区分も複雑になりやすいため、早めに税理士に相談し、名義整理や贈与計画を立てておくことが重要です。
まとめ
名義預金は、名義と実際の所有者が一致していないことで、思わぬ相続税のリスクを招く可能性があります…見た目の形式だけでなく、通帳や印鑑の管理状況、資金の出所、贈与の有無など、実質的な中身が問われる点に注意が必要です。「うちは大丈夫」と思っていても、いざという時にトラブルになるケースも少なくありません。贈与契約書の作成や贈与税の申告、預金の管理方法の見直しなど、できることから早めに備えておくことが大切です。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。少しでもご不安がある方は、個別無料相談も実施しておりますのでお気軽にご連絡下さい。あなたとご家族の大切な財産を守るために、今からできる対策を一緒に考えていきましょう。