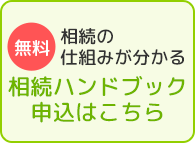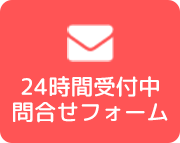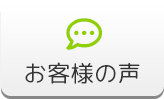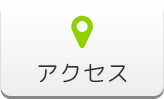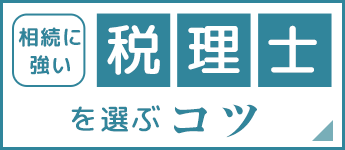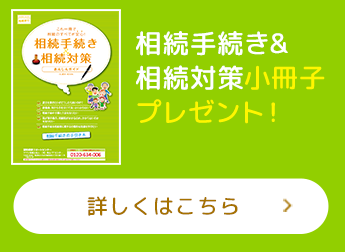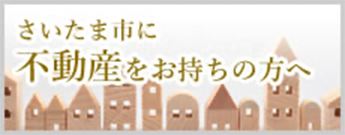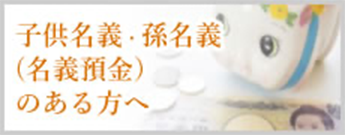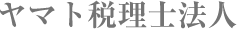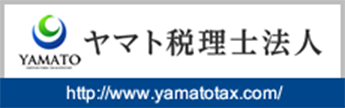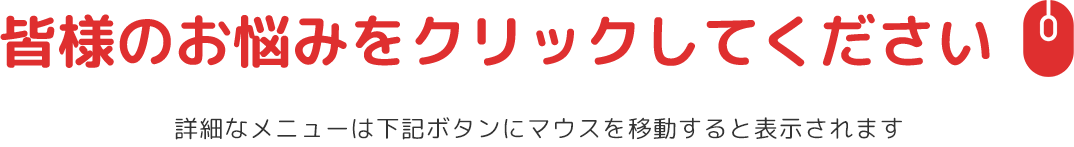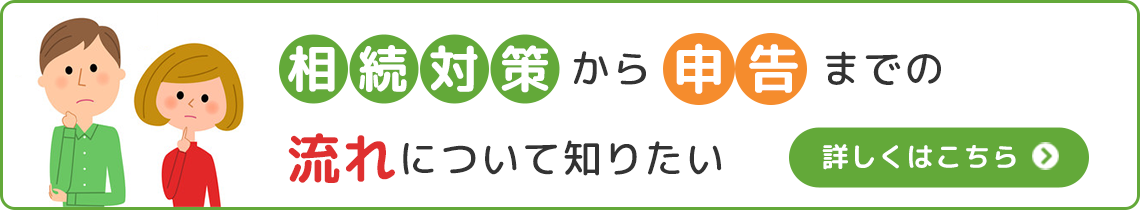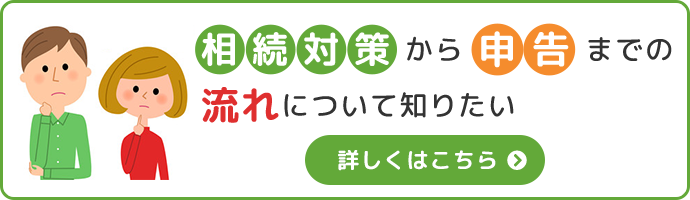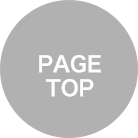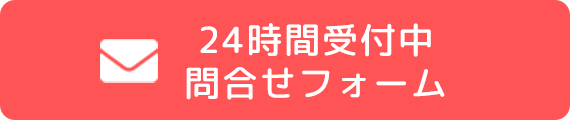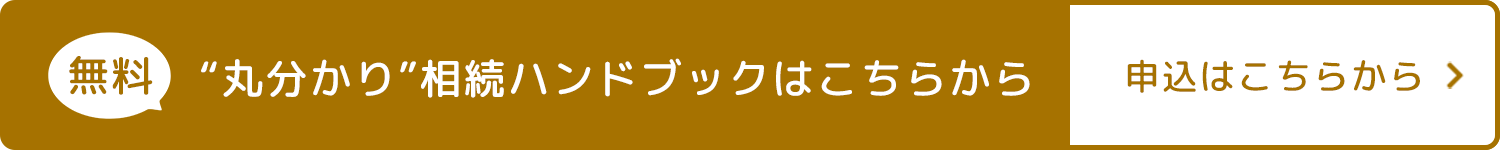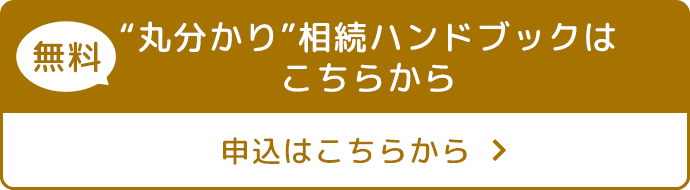【コラム】相続登記の義務化スタート!今すぐ始めるべき空き家と不動産の相続対策


こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
「親が高齢になり、そろそろ実家や土地のことも考えないと…」そう感じ始めている方は多いのではないでしょうか。特に地方に実家がある方や、親が不動産を複数所有している地主のご家庭では、「空き家の管理」や「使わない土地の処分」など、頭を悩ませる課題が山積みです。この記事では、「空き家」「利用予定のない不動産」「共有トラブル」について、わかりやすく解説していきます。
2025年問題と不動産相続:なぜ今「実家」や「土地」の整理が必要なのか?
「2025年問題」とは、団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者になることで、介護や医療、相続といった家族の課題が一気に表面化する社会的な問題です。
特に「不動産の相続」は、手続きが煩雑なうえ、空き家や管理放棄のリスクが高く、深刻な社会課題となっています。 地方に実家を持つ地主のご家族にとっては、空き家となる可能性や、使い道のない土地の扱いが悩みのタネです。 実際、「とりあえず相続してから考えよう」と思っていたら、維持費や管理コスト、売却トラブルに悩まされたというケースも少なくありません。
相続登記の義務化で不動産の放置ができない時代へ
2024年4月から、相続によって取得した不動産の登記が義務化されました。
これは、放置された空き家や所有者不明土地の増加を防ぐための法律改正です。 具体的には、相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、「10万円以下の過料」が科される可能性があります。 これまでなら「とりあえず放っておく」ことも可能でしたが、今後はそうはいきません。 この制度によって、「使わない土地や建物の相続」も明確な意思決定と手続きが必要になりました。
相続する不動産が「空き家」や「利用予定なし」の場合の選択肢とは?
地方にある実家や農地、使われていない貸家など、相続後に「住まない」「貸さない」「売れない」不動産は、いわゆる“負動産”になるリスクがあります。 相続時には、そうした物件をどう扱うか、事前に検討しておくことが重要です。
売却:早期の現金化でリスク回避
不要な土地や家は、早めに売却することで、管理コストや相続人間のトラブルを回避できます。
特に「評価額の高い土地」が必ずしも「高く売れる」とは限らず、 実際の市場価格とのギャップが数百万円あるケースも。 売却時には以下の点を事前に確認しておくと安心です。
・市場価格の調査(不動産会社2社以上に査定依頼)
・建物の解体・測量費用
・売却益が出た場合の譲渡所得税
また、空き家特例(3,000万円控除)などの税優遇制度もあるため、税理士への事前相談が鍵となります。
活用:貸す・駐車場・太陽光発電という選択肢
売却が難しい物件でも、工夫次第で収益化できる場合もあります。
たとえば、駅近なら「月極駐車場」へ転用 – 敷地が広ければ「太陽光発電用地」として活用 – 戸建住宅なら「シェアハウス」「外国人向け賃貸」などの活用など。ただし、これらには初期投資・収支計算・地元ニーズ調査などが必要不可欠。
無計画な活用は、逆に赤字を生むリスクもあるため、信頼できる不動産会社や行政の空き家対策課との連携も有効です。空き家をリフォームして賃貸に出す、駐車場や太陽光発電に活用するなどの選択肢もあります。
共有整理:兄弟姉妹での相続トラブルを防ぐ鍵
不動産を共有名義で相続してしまうと、「売りたい人」「残したい人」など意見が割れ、10年・20年と揉める原因になります。
地主のご家庭では、「兄が本家、弟は都会で仕事」といったケースも多く、継続的な管理負担の分担が難しくなりがちです。 そのため、相続前に以下のような対策を行うのが理想です。
・生前贈与で特定の子に集約
・遺言書で明確な所有者を指定
・他の相続人には代償金や別資産で調整
共有整理を事前に進めることで、相続後の意思決定がスムーズになり、不動産の価値も活かせる可能性が高まります。
相続税対策にも直結!不動産評価額を事前に把握しよう
不動産は現預金と違って評価が複雑です。
相続税では、国税庁が定めた「路線価」による評価が基本となりますが、立地や形状、利用状況によって評価額が大きく変わります。 たとえば、形がいびつな土地や道路に接していない土地は、評価額が低くなる可能性があります。 税務署との見解の違いで追徴課税になることもあるため、事前に評価を確認しておくことが大切です。
節税の鍵は「小規模宅地等の特例」の活用
被相続人の自宅や事業用地などに適用できる「小規模宅地等の特例」は、最大で80%まで評価額を減らすことができる、極めて重要な節税制度です。
この制度の適用には、以下のような条件があります。
・同居していた親族が継続して住み続ける
・相続開始時点で配偶者や居住親族がいる
・一定期間内に申告する
制度を適用することで、数百万円〜数千万円の節税効果が見込めます。
ただし、同居の有無や登記状況によっては適用できないケースもあるため、相続前から準備を進めることが重要です。
まとめ
いかがでしたか? 親から引き継ぐ不動産には、たくさんの想い出や思い入れが詰まっている一方で、管理や相続の手続き、税金の負担など、現実的な問題も避けては通れません。 「何から始めればいいのか分からない…」そんな方こそ、今のうちから少しずつ準備をしておくことで、将来の不安がぐっと軽くなります。 このコラムが、ご家族で相続について話し合うきっかけになれば幸いです。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。