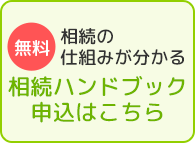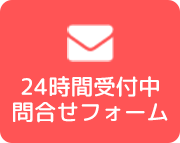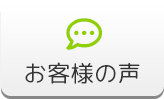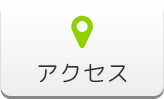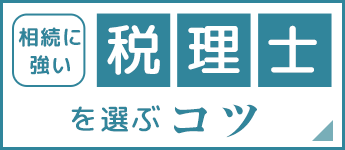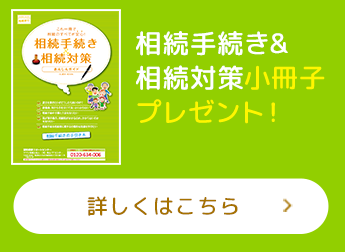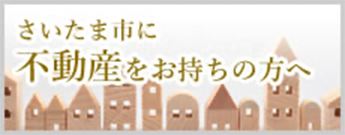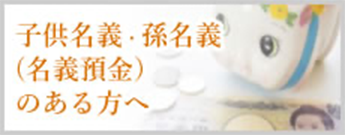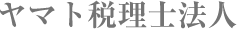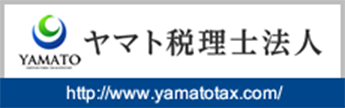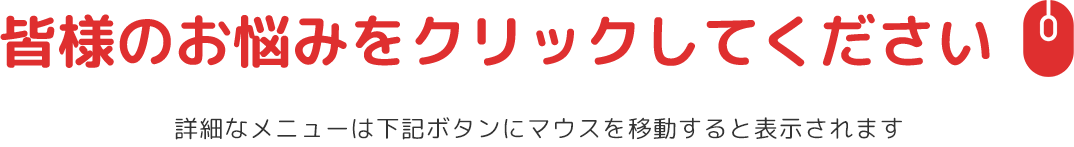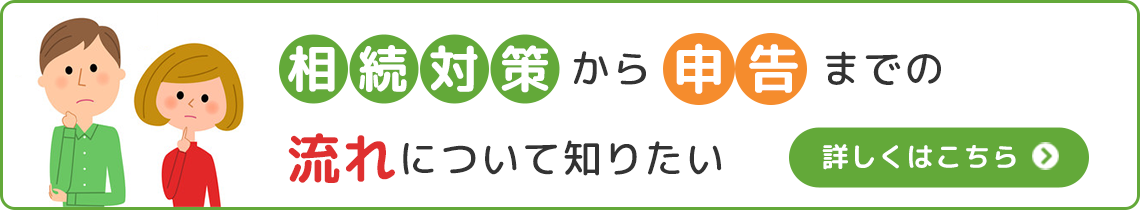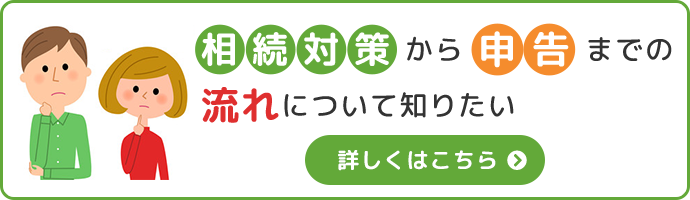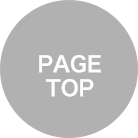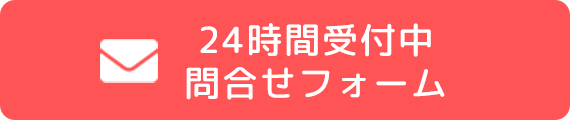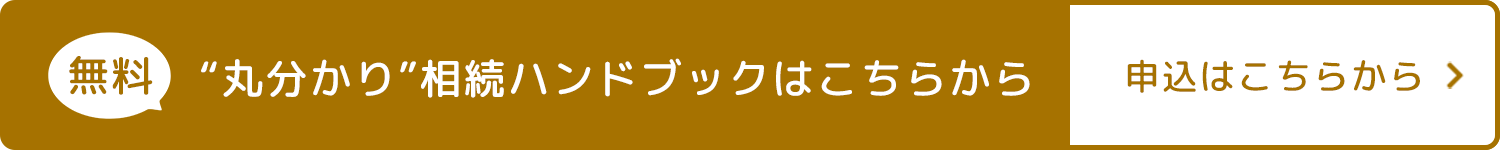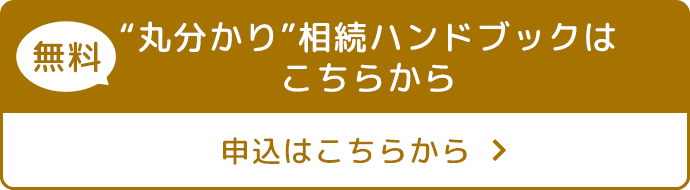【コラム】共有名義の土地、どう分ける?相続トラブルを防ぐ3つの分割パターン
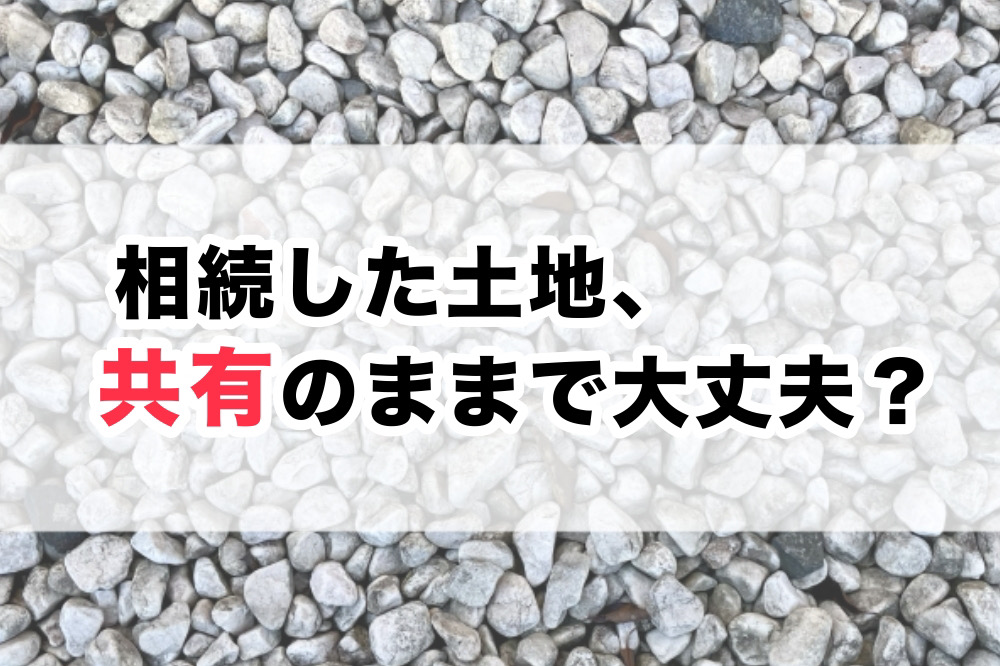
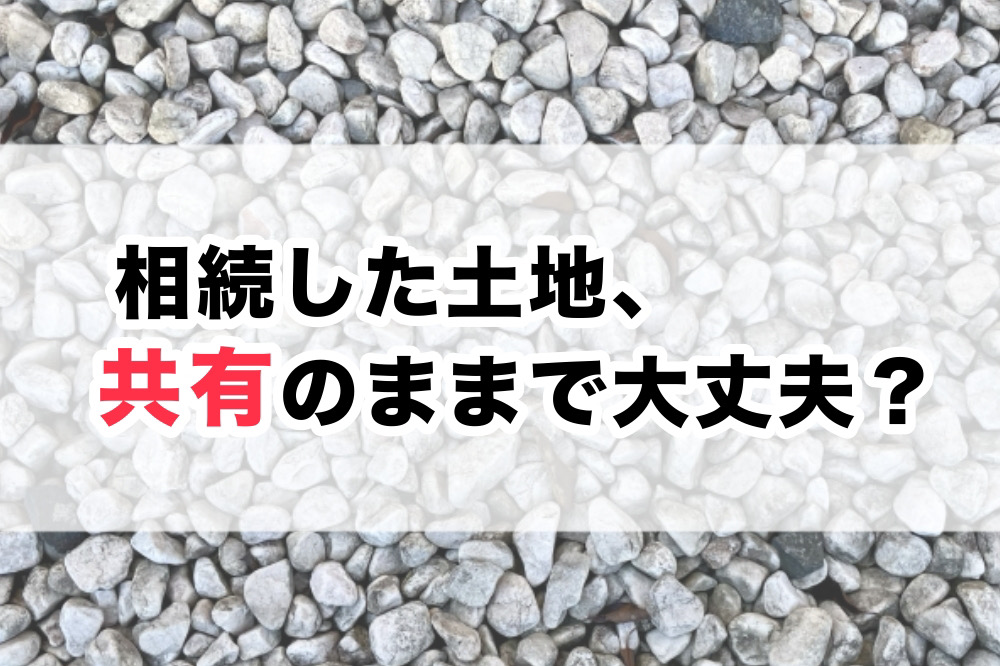
こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
「親から相続した土地が兄弟と共有名義になってしまった…」「名義が共有のままで何も活用できない」そんな悩みを抱えている方から、当センターには多くのご相談が寄せられています。 共有名義の土地は、一見公平に見えて、実は相続後に大きなトラブルの種になることもあります。特に不動産は簡単に分けることができず、「売る?貸す?住む?」といった活用の話でもめるケースが少なくありません。 この記事では、相続後に共有名義となった土地をどう分ければよいのか、代表的な3つの分割方法とその注意点をわかりやすく解説します。 相続人が複数いる方、相続手続きに不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください!
共有名義の土地とは?相続時に起こりやすい問題点
共有名義の土地とは、複数の人が一つの土地を持ち分(持分)という形で共同所有している状態を指します。相続が発生すると、法定相続分に応じて土地を分け合うケースが多く、このとき土地が「共有状態」となります。
一見、公平に見えるこの分割方法ですが、実際にはトラブルが頻発します。共有者全員の同意がなければ、土地の売却・建物の建築・貸出などができないためです。
例えば、「兄は売りたい」「弟は貸したい」「妹は住みたい」など意見が分かれた場合、土地は何も利用できず、税金と維持費だけがのしかかってきます。資産を守りつつ、無用なトラブルを防ぐ手段を知ることが重要です。
なぜ「共有名義」が相続でもめる原因になるのか?
・意思決定に全員の合意が必要で、1人でも反対すれば話が進まない
・時間が経過すると、相続人が増えてさらに複雑化
・固定資産税の支払いが不公平になりやすい
・認知症などで意思表示できない共有者が出ると、売却や分割は事実上不可能に
こうしたトラブルを避けるには、できるだけ早い段階で分割の方向性を話し合い、共有状態を解消することが求められます。
共有名義の土地、分け方は主に3つ!
共有名義になってしまった土地は、以下の3つの代表的な方法で分けることができます。ご家族の状況に応じて、最適な方法を選びましょう。
① 現物分割|土地を物理的に分ける方法
現物分割とは、土地を実際に分筆して、相続人それぞれに所有させる方法です。たとえば300㎡の土地を3人で100㎡ずつに分けるといったケースです。
メリット: ・不動産としてそのまま活用できる ・各自が自由に使用・売却できる
デメリット: ・形状や接道条件により分筆できない場合がある ・不公平な分け方になりがち ・測量や登記費用が発生
② 換価分割|土地を売却して現金で分ける方法
換価分割は、共有地を一括で売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
メリット: ・公平に分配しやすい ・不動産を処分できるので維持費不要 ・現金化できて納税や資金需要にも対応可能
デメリット: ・相続人全員の同意が必要 ・買い手がつかない可能性あり ・譲渡所得税が発生する場合がある
③ 代償分割|1人が取得し、他の人に代償金を支払う方法
代償分割は、相続人のうち1人が土地を単独取得し、その代わりに他の相続人に現金で代償金を支払う方法です。
メリット: ・土地をまとめて活用できる ・居住中の相続人がそのまま住める ・トラブル回避につながる
デメリット: ・代償金の用意が必要 ・公平性について他の相続人から不満が出る可能性 ・税務上の贈与とみなされるリスクあり
図解|土地分割方法の比較シミュレーション
以下の表は、土地を3,000万円相当とした場合の各分割方法の比較です。
| 分割方法 | 土地価格(評価額) | 相続人Aの取り分 | 相続人Bの取り分 | 相続人Cの取り分 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現物分割 | 3,000万円 | 土地150㎡ | 土地150㎡ | 接道なし土地150㎡ | 土地をそのまま残せる/不動産活用ができる | 分筆が難しい土地は使えない/不公平になりがち |
| 換価分割 | 3,000万円 | 1,000万円(現金) | 1,000万円(現金) | 1,000万円(現金) | 現金で分配され公平/トラブルが少ない | 買主が見つからない可能性/譲渡所得税が発生 |
| 代償分割 | 3,000万円 | 土地全体(300㎡) | 代償金1,000万円 | 代償金1,000万円 | 土地の一体利用が可能/相続人が住み続けられる | 代償金の支払い負担が重い/公平性の議論が起こりやすい |
Q&A|共有名義の土地でよくある質問
Q1. 相続人の一人が認知症になったら、どうなりますか?
A. 認知症と診断された方がいると、その人が意思表示できないため、土地の処分や分割協議は行えません。家庭裁判所を通じて成年後見人の選任が必要となり、一定の時間と手続きがかかります。
Q2. 換価分割で売った場合、譲渡所得税がかかる?
A. 売却によって利益が出た場合は譲渡所得税が発生します。ただし、相続発生後3年以内の売却であれば、取得費加算の特例が適用され、税負担を軽減できます。必ず税理士に確認しましょう。
Q3. 代償金の支払いは贈与になる?
A. 原則として贈与税はかかりませんが、著しく不公平な分け方や説明ができない場合は、税務署に贈与とみなされる可能性もあります。分割協議書の作成と記録の保存が重要です。
まとめ
相続でもらった土地が共有名義のままになっていると、思わぬトラブルや負担を招いてしまうこともあります。「なんとなく面倒で…」と先延ばしにしている方も多いですが、早めに動くことで、解決の選択肢もぐっと広がります。 ご家族それぞれの希望や事情を尊重しつつ、専門家と一緒に最善の形を見つけていきましょう。 もし「自分たちの場合はどう進めるのがいいのか分からない」と感じているなら、ぜひ一度ご相談くださいね。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。