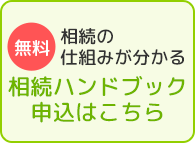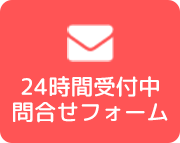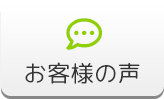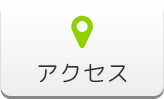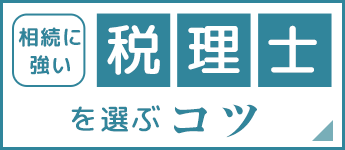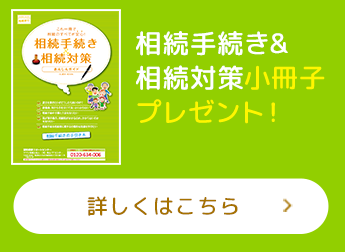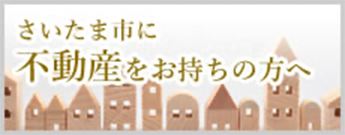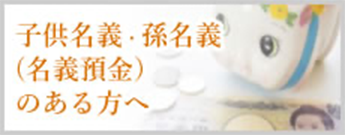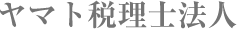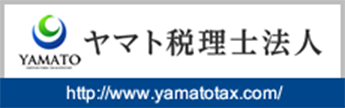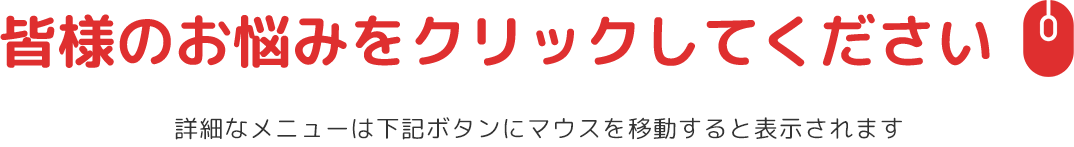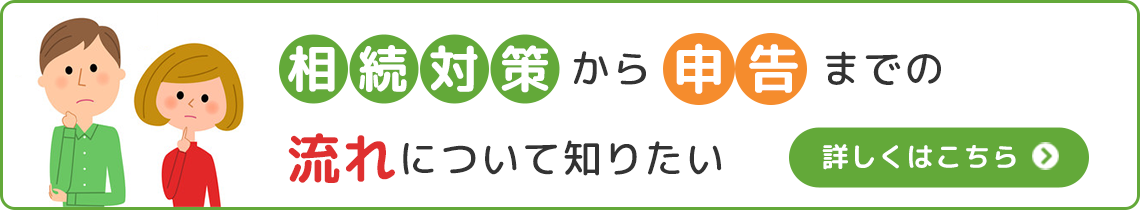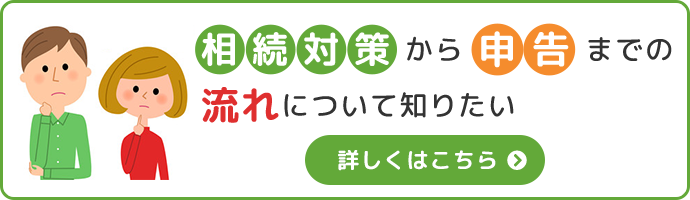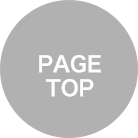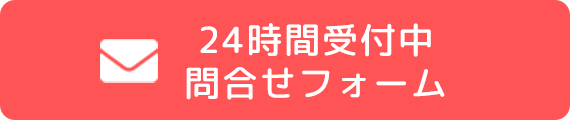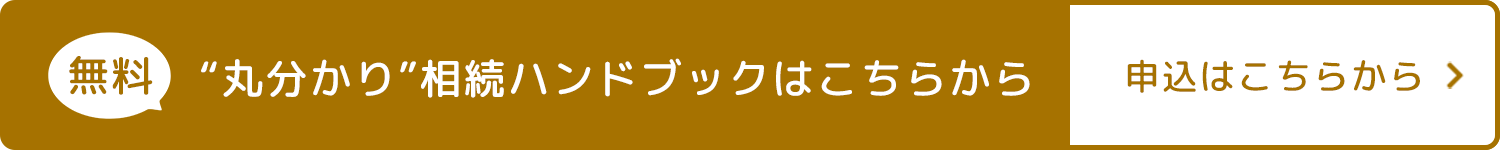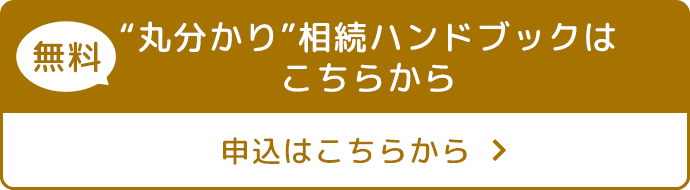【コラム】相続税の申告は自分でできる?ケース別に徹底解説
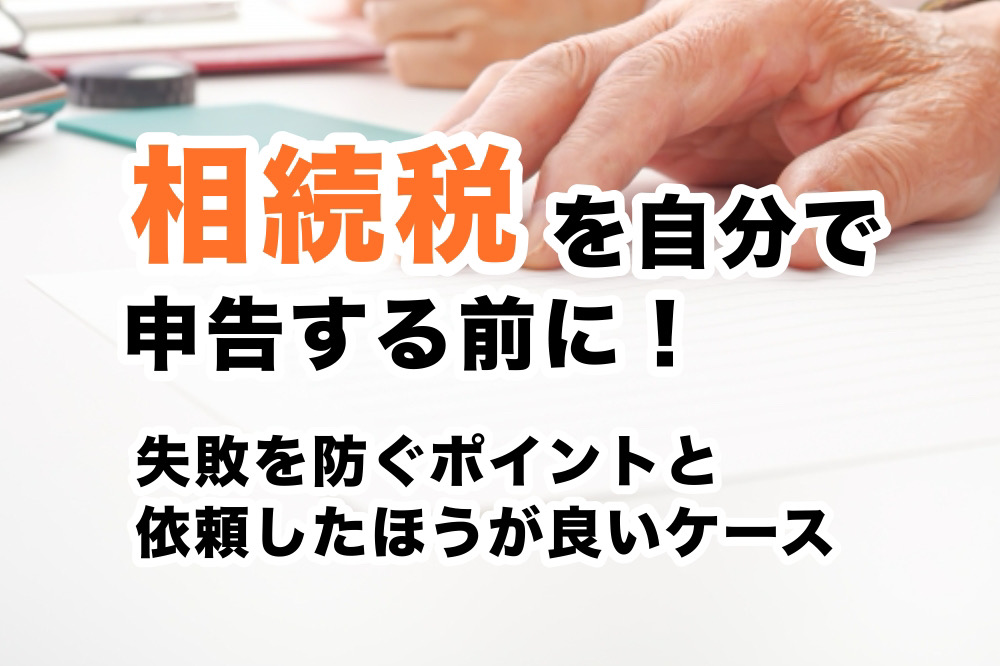
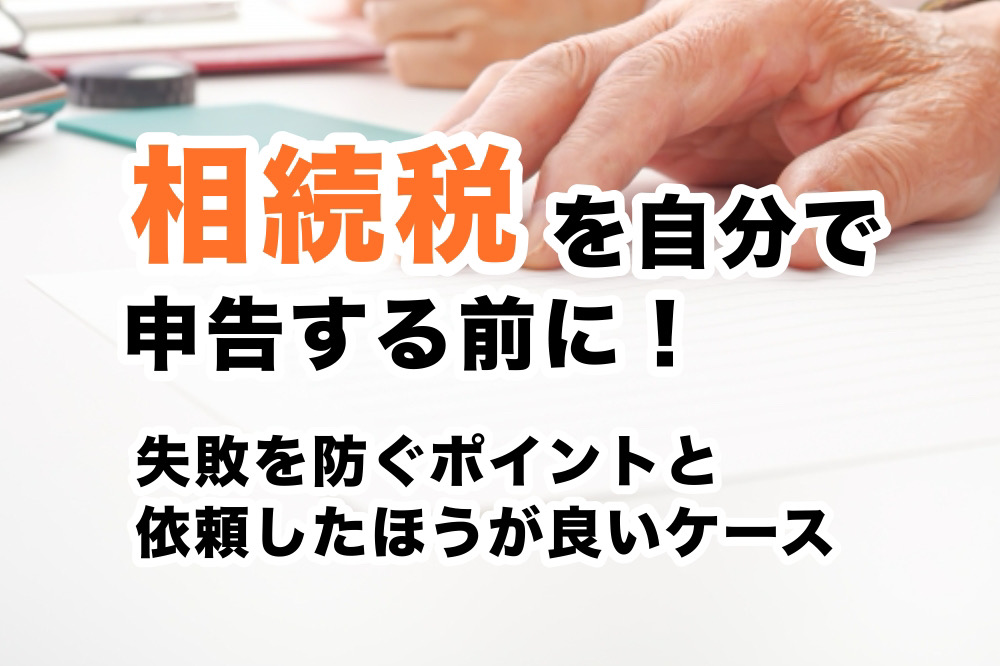
こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
「相続税の申告って、自分でできるの?」「税理士に依頼するといくらかかるの?」――初めて相続を経験される方の多くが、こうした不安を抱えています。浦和エリアでも、近年は「相続を自分でやってみたい」と考えるご家族が増えていますが、手続きの煩雑さや専門的な評価が壁となることも少なくありません。この記事では、相続税申告の流れ・必要書類・自分でできる範囲・税理士に依頼すべきタイミングを徹底解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
相続税申告の基本|誰が・いつまでに行う?
相続税申告は、すべての相続で必要というわけではありません。課税対象となるのは、遺産総額から債務・葬儀費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える場合のみです。 基礎控除の計算式は次の通りです。
| 項目 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 相続人3人の場合 → 4,800万円 |
この金額を超えると申告義務が発生し、相続開始(亡くなった日の翌日)から10か月以内に税務署へ申告・納税します。 遅れると「無申告加算税(最大20%)」や「延滞税」が課されるため、期限管理が重要です。
相続税の申告を自分で行う流れ
相続税の申告は法律上、本人でも可能です。しかし、実際には「申告書の作成・財産評価・特例の適用」など高度な判断を伴う工程が多くあります。以下の4ステップで進めましょう。
ステップ①:相続人と相続財産を確定する
まず、戸籍謄本・除籍謄本をすべて取得し、相続人を確定します。その後、預貯金・不動産・株式・生命保険など、あらゆる財産を一覧化します。 特に注意が必要なのは、名義預金や生前贈与の取り扱い。相続人名義でも実質的に被相続人の資金であれば、相続財産に含まれます。
ステップ②:財産評価を行う
土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産評価額、株式は市場価額をもとに評価します。 たとえば浦和の住宅地では、路線価が坪当たり60万円前後の場合もあり、評価誤りが税額に大きく影響します。 国税庁の「路線価図」や「財産評価基準書」を確認しながら進めましょう。
ステップ③:申告書の作成・提出
相続税申告書は第1表~第15表までで構成されており、財産の種類ごとに異なる欄を記載します。 提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署。 添付書類の不足や記入ミスがあると、受理されず修正を求められることがあります。
ステップ④:納税方法を選択する
納付は原則現金ですが、資金が足りない場合は延納(分割払い)や物納(不動産・株式などで納付)も可能です。 ただし審査が必要で、手続きも煩雑なため、早めの準備が欠かせません。
相続税申告に必要な書類一覧
申告に必要な書類は大きく分けて「相続人関係」「財産関係」「控除関係」の3種類です。
相続人関係の書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印)
財産関係の書類
・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書
・預貯金残高証明書・有価証券の残高証明
・生命保険金の支払通知書・車検証・貴金属の鑑定書
控除・特例の書類
・配偶者控除・小規模宅地特例の適用届出書
・障害者控除・未成年者控除の証明資料
Q&A|自分で申告するときのよくある疑問
Q1. 相続税申告を完全に自分で行うことは可能?
A. 可能ですが、「できる」と「成功する」は別問題です。 税務署の無料相談では一般的なアドバイスは受けられますが、個別の節税策や評価の最適化まではサポートされません。 不動産や株式を含む相続では、専門家の確認を受けた方が安全です。
Q2. ミスをしたらどうなる?
A. 申告漏れや評価誤りがあると、後日税務調査で修正申告を求められ、追徴税が発生します。 加算税・延滞税を含めると、本来の税額の1.2~1.5倍に膨らむこともあります。
Q3. 相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は?
A. 期限を過ぎても申告は可能ですが、「無申告加算税(15~20%)」と「延滞税」が課されます。 遅延が分かった段階で、すぐに税理士に相談し、自主的に申告を行えば、ペナルティが軽減されるケースもあります。
税理士に依頼すべきケースと費用シミュレーション
路線価補正・間口奥行・地積規模の大きな宅地等の判定、類似業種比準価額など高度な評価が必要。
特例の選択や組み合わせにより税額が大きく変動。要件と添付書類を期限内に揃える必要あり。
一次相続と二次相続の合計最適化、代償分割・換価分割・共有解消の設計が必要。
延納・物納は審査と書類要件が厳格。早期計画と資金繰り設計が不可欠。
立証資料の整備や資金移動の実態把握が重要。専門家の事前点検でリスクを低減。
遺産総額・財産構成・相続人の数・特例適用の有無で報酬は変動します。以下は目安であり、正式なお見積りは個別無料相談で算定します。
まとめ
相続の手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。だからこそ、分からないことや不安があって当然です。「これで合っているのかな?」と思ったときこそ、早めの相談が安心への第一歩です。浦和相続サポートセンターでは、相続税申告から名義変更・生前贈与のご相談まで、経験豊富な税理士が丁寧にサポートいたします。気になることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの相続が、安心して次の世代につながりますように。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。