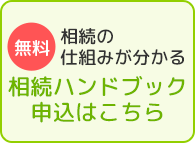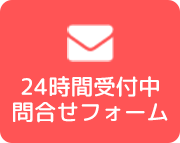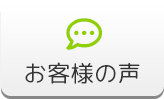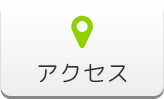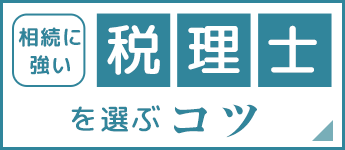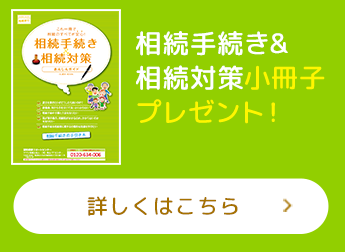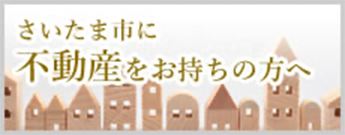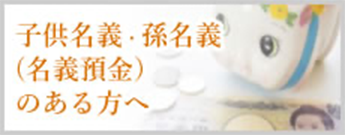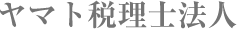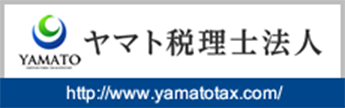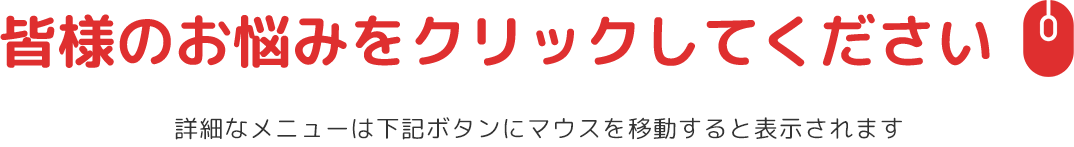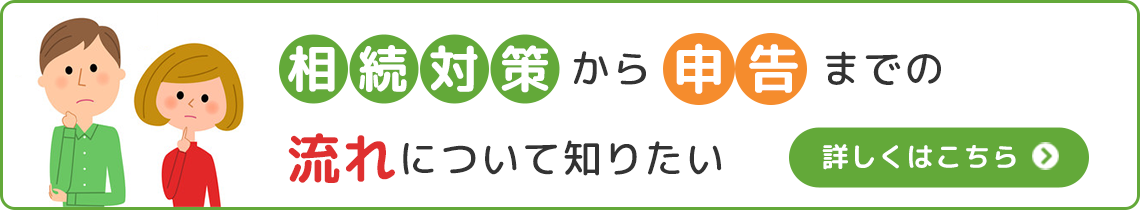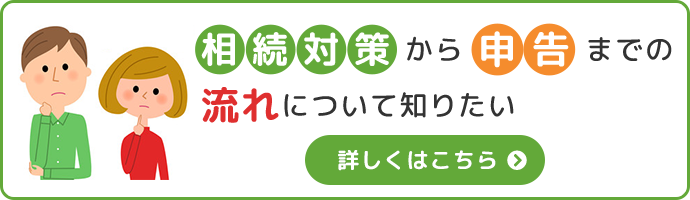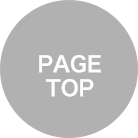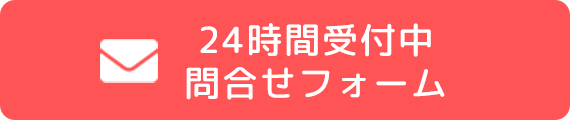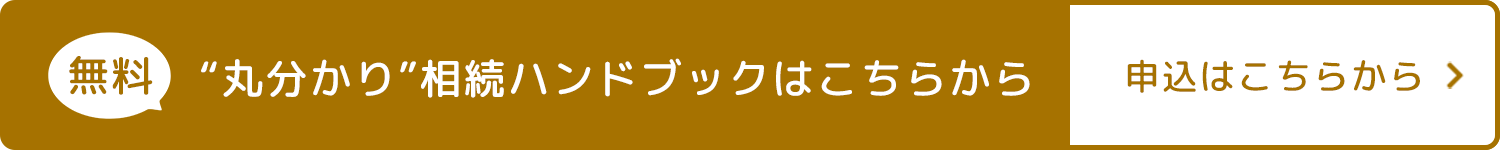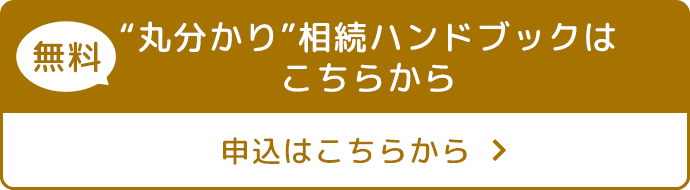【コラム】“何もしない”は一番危険!親の認知症に備える相続対策完全ガイド
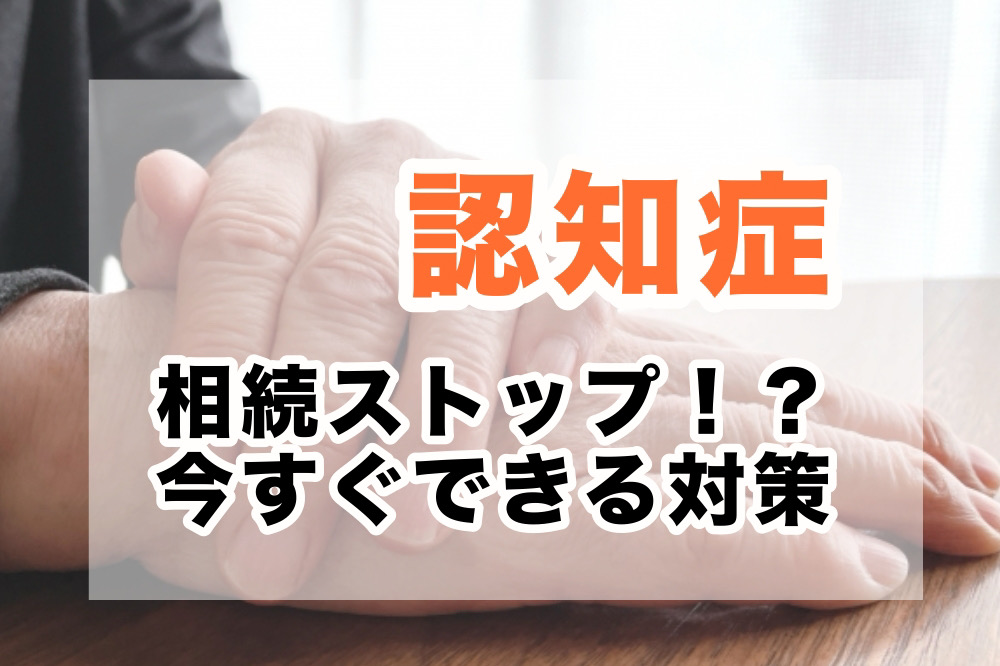
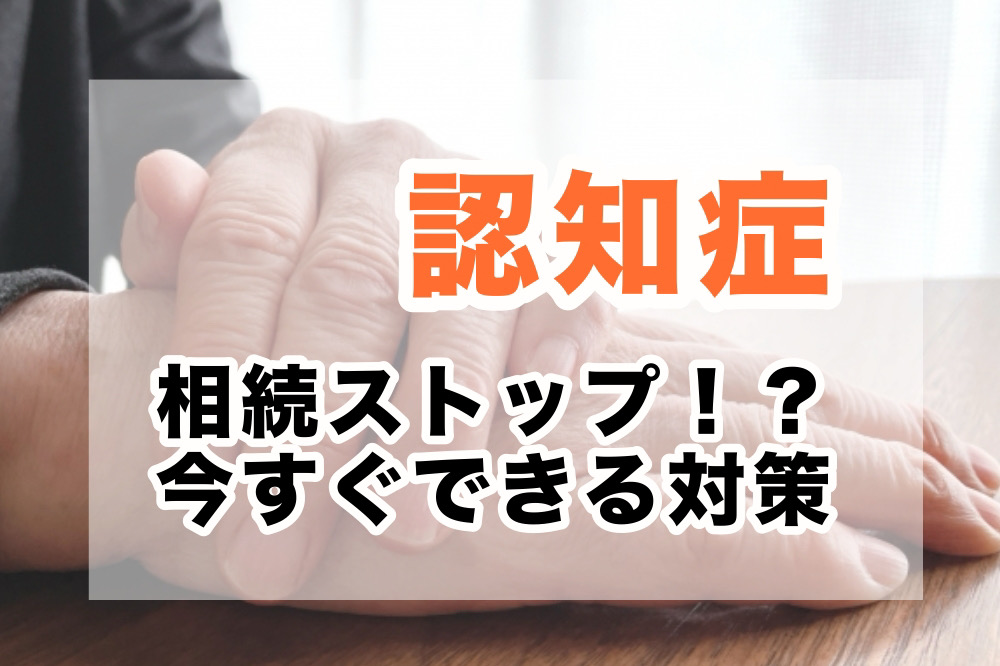
こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
「親が認知症と診断されたけど、もう相続の準備はできないの?」というご相談をいただくことが増えています。相続は“元気なうち”に準備をするのが基本です。 この記事では、「親が認知症になった場合の相続への影響」と「今すぐできる準備」、さらに「地主の方が特に注意すべき点」について、わかりやすく解説していきます。 親が高齢になり今後の相続を心配されているご家族は、ぜひ最後まで読んでみてください!
認知症になると相続対策が進められなくなる理由
相続対策の基本は「本人の意思」が確認できることです。しかし、認知症によって判断能力が低下すると、下記のような手続きが困難になります。
-
・遺言書の作成(遺言能力が必要)
・不動産の名義変更(意思確認が必要)
・生前贈与(契約意思が必要)
つまり、「できる時期にしかできない対策」が多く、親が認知症になる前に動く必要があるのです。地主のように資産が多岐にわたる場合は、より早急な対応が求められます。
Q&A|よくあるご相談とその回答
Q1:親が認知症と診断されました。遺言書はもう作れませんか?
医師の診断書で「遺言能力あり」と判断されれば作成可能ですが、裁判で無効とされるリスクもあります。安心のためには、早めの公正証書遺言をおすすめします。
Q2:成年後見制度を利用すれば大丈夫ですか?
成年後見制度は「資産の保護」が目的であり、「相続税対策や不動産売却」などには制約があります。柔軟な対応ができる家族信託との併用が効果的です。
Q3:地主である父の不動産を生前に整理したいのですが?
家族信託で子が財産管理の権限を持てば、不動産の売却・修繕・賃貸契約もスムーズに進められます。相続後の“共有名義”によるトラブルも防止できます。
【図解】相続対策の可否とリスク
以下の図は、親が認知症になる前後で、どのような相続対策が可能かを示したものです。
| 相続対策 | 認知症前 | 認知症後(成年後見なし) | 認知症後(成年後見あり) |
|---|---|---|---|
| 遺言書の作成 | ○ | × | ×(原則不可) |
| 生前贈与 | ○ | × | × |
| 不動産の名義変更 | ○ | × | △(家庭裁判所の許可が必要) |
| 家族信託 | ○ | × | × |
【比較表】対策別の費用とリスクシミュレーション
実際の相続対策では、費用対効果の検討が重要です。以下は、代表的な対策の費用とリスクを比較した表です。
| 対策内容 | 初期費用の目安(円) | 将来のトラブル発生リスク | 相続人間の揉め事防止 |
|---|---|---|---|
| 何もしない | 0 | 高 | × |
| 公正証書遺言作成 | 100,000 | 中 | ○ |
| 家族信託 | 300,000 | 低 | ◎ |
| 成年後見制度 | 200,000 | 中 | ○ |
| 家族信託+遺言 | 350,000 | 低 | ◎ |
よくある誤解とそのリスク
相続の現場では、誤解や思い込みから「何もしない」ことが最大のリスクになります。 以下のような考えに心当たりがある方は、要注意です。
「まだ元気だから大丈夫」は危険な先延ばし
認知症は突然やってきます。 「まだ自分で動けるから」と思っていても、ある日突然意思判断ができなくなり、手続きが一切できなくなるリスクがあります。
特に、不動産を多く持つ地主の方は、相続人間の調整に時間がかかる傾向があります。“できるうちに”対策を始めることが、将来の安心につながります。
「配偶者が元気だから大丈夫」は誤解
配偶者が元気でも、法的な判断は「本人の意思」が最優先です。 たとえ妻や夫が代わりに動こうとしても、本人が認知症になっていた場合、財産の移動は認められません。
家族で支えあっていれば問題ないという“情の論理”は、法律の世界では通用しません。事前の仕組みづくりが重要です。
「認知症でも遺言が書ける場合がある」は本当だが条件あり
実は、認知症になっていても「遺言能力がある」と判断されれば、遺言書を作成することは可能です。 しかし、医師の診断書や面談記録などの客観的証拠が求められ、証明のハードルは非常に高くなります。争いを避けるためには、「明確な時期に」「法的に有効な手続き」で作成しておくことがベストです。
地主だからこそ必要な「複数対策」の視点
地主の方は、不動産の数や種類が多いため、相続対策が複雑化しがちです。
・地目や地積の整理
・納税資金の確保(現金化可能な資産の準備)
・相続人ごとの分配方法の明確化
家族信託と遺言の“組み合わせ”や、不動産の一部売却による納税資金の確保など、「複合的な設計」が必要です。地主の相続は“制度の知識”と“実務の経験”の両方が問われます。
まとめ
もし「ウチはまだ先の話かな」と思っていたら、今日がその第一歩かもしれません。認知症と相続の問題は、突然やってくるからこそ、“準備しておけばよかった”という声が多いのです。不安をそのままにせず、「いまできること」から始めてみませんか? きっと、将来の自分や家族が「やっておいてよかった」と思える日が来ます。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。