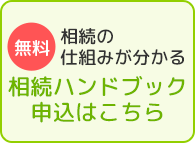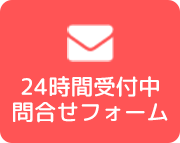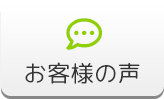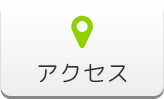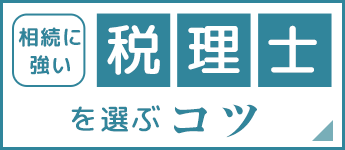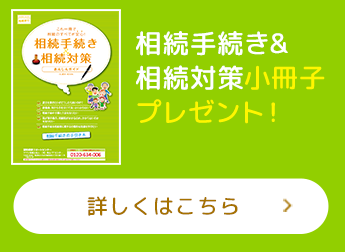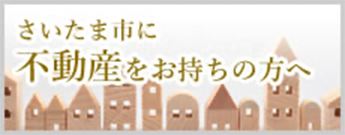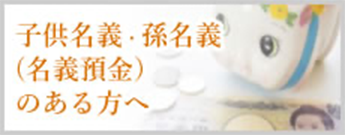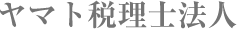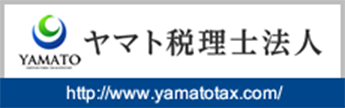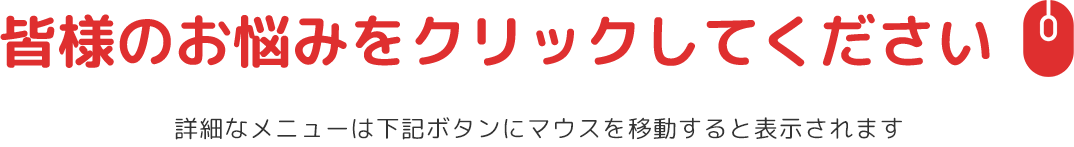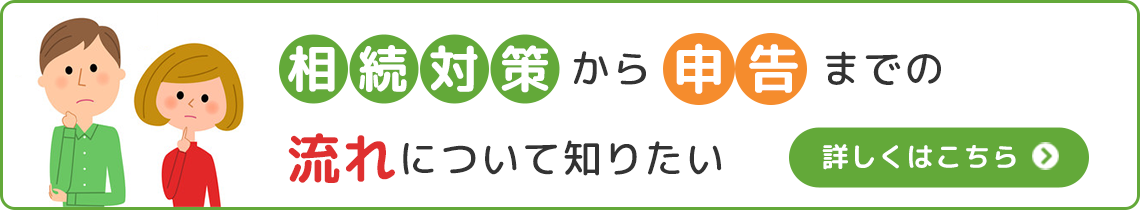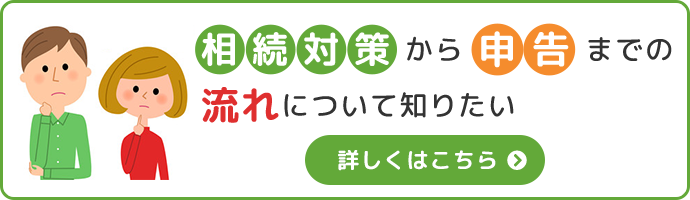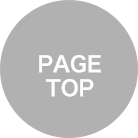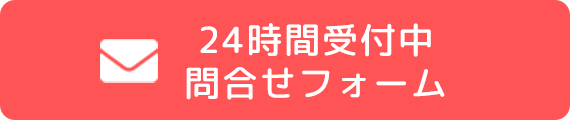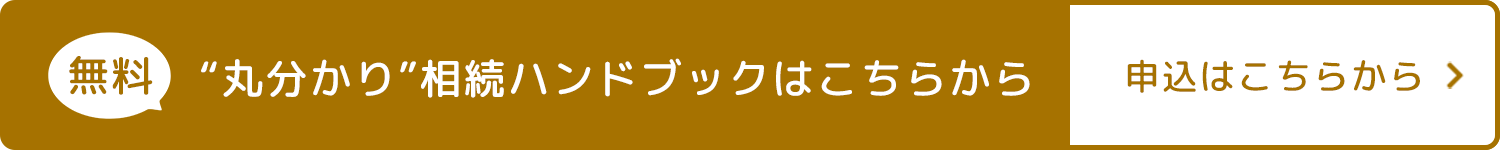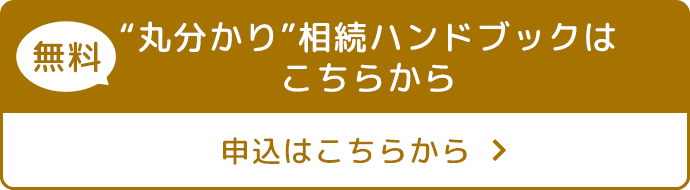タワーマンション節税-相続税の課税に関して-
タワーマンションが節税対策の手段として用いられている事をご存知でしょうか?
テレビなどでよく見かけるのは、高層階の固定資産税が低階層のそれに比して割安であるといった話です。しかし、それは1年あたり数万円程度の固定資産税の差額であり、誤解を恐れずに言えば、さほど大きな問題ではありません。本当に問題なのは、何千万円もの課税価格の減額をもたらす相続税の節税効果です。

今回はタワーマンションの相続税の課税に関してお話させていただきます。
相続税において、分譲マンションのような区分所有建物は、土地と建物を別々に評価し、それを合算して1戸の評価額を算出します。大雑把に言うと、土地は相続税路線価の価格に基づいて、建物は固定資産税評価額に基づいて評価を行います。
上記の評価を行うと、市場価格と相続税評価額にかい離がでてきます。地域によって差がありますが、相続税評価額は、土地の評価の場合は市場価格より2から4割、建物の評価の場合には新築価格より3割から5割程度低くなると言われています。
では、具体的にどのように相続税の節税効果が得られるのでしょうか。
例えば、Aさん(被相続人)が亡くなる直前に1億円で購入したタワーマンションをBさん(相続人)が相続した際に、タワーマンションの相続税評価額が6千万円になったと仮定します。その場合、Bさんは6千万円分の財産について相続税を支払えばよいことになります。つまり、1億円のタワーマンションを購入し、相続税の申告後に購入価額の1億円で売却をして1億円の現金を得るほうが、現金を1億円相続するよりも、相続税が格段に安く抑えられ節税効果が見込めるということになるのです。
このように、タワーマンションの購入は節税効果が非常に高いため、富裕層の間でこの節税方法が大流行しました。しかし、この行為には相続税の減額以外に合理的な目的が認められず、行き過ぎた節税だとして国税当局が対策にのりだしました。そして、財産評価基本通達6項という条文によって、いくつかの事例が否認されています。
この財産評価基本通達6項とは、「この通達(財産評価基本通達)の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められているもので、過去の裁決事例をみると、この条文は「市場価格とのかい離」だけでなく「個別的な要素」を考慮したうえで、適否を判断しているように見受けられます。投資目的の保有等、節税以外の保有目的を有していると客観的に判断できるのであれば、市場価格と相続税評価額がかい離していても、同条文に該当しない可能性もありますが、保有目的が節税のためだけであると客観的に捉えられるのであれば、否認される可能性が出てきます。
タワーマンション節税に関する直接的な相続税の改正は現在のところ行われておりません。しかし、改正も含めて今後の動向を見守り、過度な節税対策になることの無いよう、気を付けていかなければならないでしょう。
法改正がありました
2024年1月1日以降の相続・贈与から、タワーマンションを含む区分所有マンションの相続税評価方法が見直されました。
従来は、タワーマンションの相続税評価額が市場価格よりも大幅に低いケースがあり、これを利用して相続税を節税する「タワマン節税」が問題視されていました。
今回の改正では、評価額と市場価格の乖離を縮めることを目的として、新たな評価方法が導入されました。具体的には、以下の点が変更されています。
-
評価乖離率の導入: 市場価格と相続税評価額の乖離率を算出し、乖離率が大きいほど評価額を引き上げる仕組みが導入されました。
-
評価水準の導入: 評価乖離率に基づいて評価額を調整し、市場価格の60%以上となるように補正する仕組みが導入されました。
これらの改正により、タワーマンションの相続税評価額は従来よりも高くなる傾向にあり、タワマン節税の効果は大幅に縮小しました。
特に、高層階で価格の高いタワーマンションほど、改正の影響を受けやすくなっています。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
|
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
|
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
|
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
|
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
|
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
|
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
|
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
|
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ


1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ


(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ


相続の無料相談会について
専門家による無料相談


無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
メールのお問合せはこちら