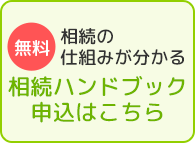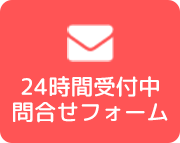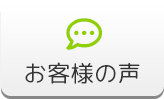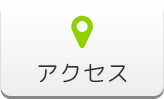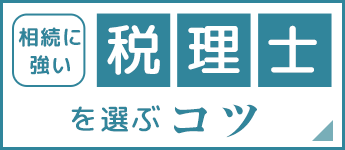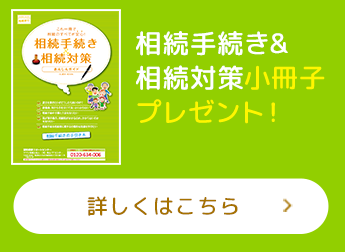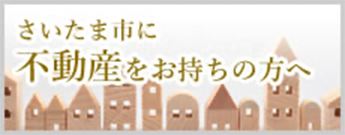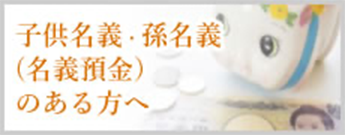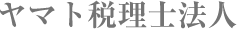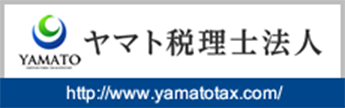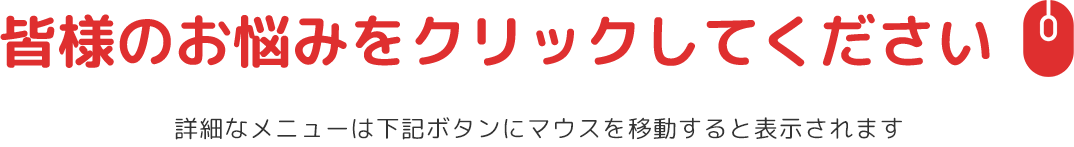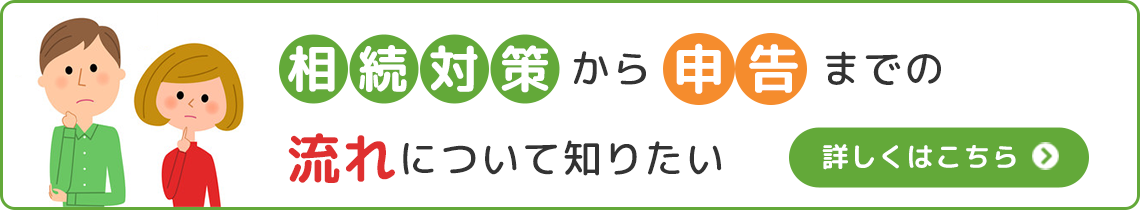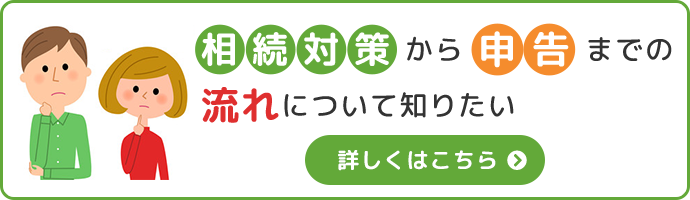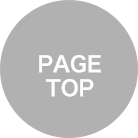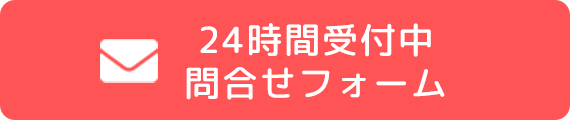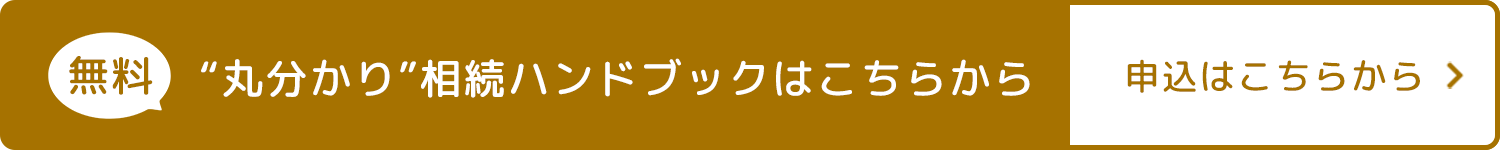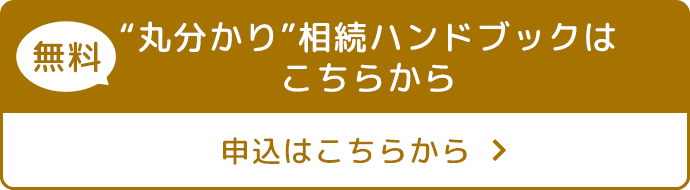事業継承税制
平成30年度の税制改正において、「従来からの非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の一部改正に加え、平成30年度からの10年間の特例措置として、「納税猶予の対象となる株式数の上限の撤廃や相続税の猶予割合の拡大などがされた制度」が創設されました。
今後10年間は、従来からの制度と新たに創設された制度が並行して存続することになりますが、今回は、創設された制度の主要な部分について書いてみたいと思います。
はじめに、従来の制度における納税猶予適用件数は、下表のとおりです。
必ずしも期待したほどの適用件数ではないように思われます。その理由として考えられるのは、納税猶予制度そのものが複雑で、手続きが煩雑、適用要件に伴うリスクに対する敬遠、認定申請など各種書類の作成に相当の事務量を要することなどではないでしょうか。
今回の新しい制度の創設により、これまで以上の飛躍的な適用件数の増加が期待されていると考えられます。
◎従来の制度での納税猶予適用件数(出典:会計検査院)


創設された制度の主要な部分(従来の制度と異なる部分)
⑴ 特例対象となる株式数には上限がなく議決権株式数の全て、また、相続税の猶予割合も100%対象株式数の適用上限(3分の2まで)を撤廃し、議決権株式数の全て(3分の3)が猶予対象とされました。また、相続税については、納税猶予割合が80%から100%に拡大されました。なお、贈与税については、従来から100%です。
⑵ 経営承継期間の8割の雇用確保要件の実質的撤廃8割維持の雇用確保要件が実質的に撤廃されました。雇用確保割合が8割を下回っても猶予を継続する場合には、下回った理由を都道府県知事に報告し、その確認を受ける必要があります。また、その理由が経営悪化が原因である場合には、認定経営革新等支援機関による経営力の向上に係る指導・助言を受けた旨が記載された報告書の写しを都道府県知事に提出する必要があります。
⑶ 特例適用対象者の拡充
特例経営承継受贈者、特例経営承継相続人等ともに、最大3人まで可能となりました。なお、複数で承継する場合には、それぞれが承継会社の株式に係る議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合が上位2位又は3位までの同族関係者に限られます。また、「代表者以外の者」から代表者である後継者への贈与も併せて対象となりました。この「代表者以外の者」からの贈与、相続については、その前に行われている代表者からの贈与、相続に係る申告書の提出期限から5年以内(承継期間)に、代表者以外の者からの贈与、相続に係る申告書の提出期限が到来するものに限られます。
⑷ 経営環境の変化(譲渡、合併消滅、解散等)に応じた納税額の減免
承継会社に「事業継続が困難な事由」がある場合において
・承継会社株式の全部又は一部を譲渡した場合
・承継会社が合併により消滅した場合
・承継会社が株式交換等により他の会社の完全子会社となった場合
・承継会社が解散した場合
これらの事由に該当することとなった場合には、譲渡の対価の額、合併対価の額、交換等対価の額を基に相続(贈与)税額を再計算し、再計算した税額と直前配当等の金額の合計額が当初の納税猶予税額を下回るときは、その差額は免除されることになりました。(再計算した税額は、納付する。)
なお「事業継続が困難な事由」については、措置法施行令40の8の5第 22項及び令40の8の6第20項に定められていますが、本稿においては記載を省略します。
⑸ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
その年の1月1日において20歳以上である特例経営承継受贈者が特例贈与者の推定相続人以外の者(特例贈与者の孫を除きます。)であり、かつ、特定贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、特例経営承継受贈者に相続税法21条の9(相続時精算課税)の規定が準用されます。
2 創設制度の適用を受けるための前提要件
⑴ 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年以内に、円滑化法2条に規定する中小企業者が作成した「特例承継計画」を都道府県に提出し、同法12条1項の認定を受けることが必要です。
⑵ 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与、相続等により、特例認定(贈与)承継会社の株式を取得することが必要です。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
|
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
|
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
|
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
|
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
|
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
|
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
|
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
|
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ


1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ


(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ


相続の無料相談会について
専門家による無料相談


無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
メールのお問合せはこちら